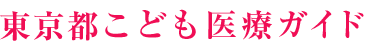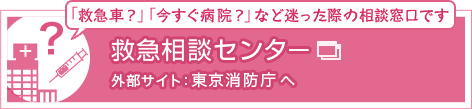基礎情報開く
インフルエンザってなに?
普通の風邪よりも症状が強く出て、突然の高熱、悪寒(おかん)で始まります。毎年のように流行がみられますが、型を変えて流行します。急に症状が重くなることもあり注意が必要です。
緊急度は?
症状によって異なります。
かかりやすい月齢/年齢は?
あらゆる年齢にみられます。
かかりやすい季節は?
冬、12月~3月です。
病気の特徴開く
潜伏期間は平均2日(1~4日)です。
普通の風邪と違い、症状が重くなります
普通の風邪とインフルエンザは同じではありません。
症状が重くなり、全身の症状が出ます。
インフルエンザは普通の風邪の喉の痛みや鼻水の症状に加え、39℃くらいの高熱や関節痛、筋肉痛などの全身症状が強く出ます。また、吐き気や嘔吐(おうと)、下痢などの胃腸症状があらわれることがあります。
合併症として中耳炎や肺炎、脳炎などを引き起こすことがあります。
原因・予防法・治療法開く
インフルエンザウイルスが鼻や喉などについて、せきやくしゃみでひろがります。
インフルエンザウイルスとは
インフルエンザウイルスはA型、B型、C型に分類されます。
| 型 | 特徴 |
|---|---|
| インフルエンザA型 | ・ 高熱、倦怠感(けんたいかん)、頭痛、筋肉痛、関節痛など全身症状が著明 |
| ・ 約10年ごとに世界的大流行を起こす ・ 1918年に世界的大流行したスペインかぜは2,000万人以上が死亡 ・ 香港かぜ、ソ連かぜなどもよく知られている |
|
| インフルエンザB型 | ・ A型の症状に比較し、やや軽症 ・ 散発的あるいは局地的な流行を起こす |
| インフルエンザC型 | ・ A型、B型の症状に比較し、軽症 ・ 発症が著しく少ない |
- 帰宅時にうがい、手洗いをする。
- 外出時にマスクをする。
- 適度な湿度を保つ[空気が乾燥するとかかりやすくなる]。
- 流行前に予防接種を受ける[10月末から11月初めにかけてがよいでしょう]。
- 流行してきたら人混みを避ける。
[特に高齢者、持病のある人、疲れ気味の人、寝不足の人]
小さいお子さんや高齢者などは予防接種を
流行は12月末~3月にかけてなので流行の始まる前に予防接種(厚生労働省が推奨している不活性化ワクチンの場合、13歳以下は2回接種)を済ましておきます。
特にかかった時に重くなることのある5歳ぐらいまでのお子さん、呼吸器や心臓に病気のある人などは予防接種をしましょう。
予防接種を希望する人は他の予防接種とは違い、毎年接種するようになります。ワクチンによる効果は3か月程度であることと、毎年流行するインフルエンザの型が違うためです。
受診時の注意点
インフルエンザは迅速検査で診断が可能ですが、発症早期は偽陰性(インフルエンザであっても陽性にならない)が多くなります。発熱以外の症状が強くなければ発熱して12時間から24時間後に受診しましょう。
最近はインフルエンザウイルスに効く治療薬(内服薬や吸入薬等)が処方されることが多いですが、発症から48時間以内に治療開始することで効果が期待できます。
治療薬は注意事項があるので、薬の説明をよく聞いて使用法をよく守ってください。
対処法・家庭でのケア開く
観察が大切です
<熱を測り、その他の全身の症状を正確に記録しましょう。>
熱があるときは、朝・昼・夕方・夜(深夜)と1日4回測り、熱だけでなく、前回測定した時からの熱の上がり方[急に上がってきた、夕方~夜になると高熱が出る、など]にも注意してみましょう。- 家にある解熱剤〔熱さまし〕を勝手に使用しないようにしましょう。
- 体温の測り方・・・脇の下は汗がたまりやすいのでよく拭き、ななめ前下の方から、脇の下の中央に体温計の先端がくるようにはさみましょう。
- 体調のよい時に熱を測り、お子さんの平熱を知っておきましょう。
- 観察ポイントは、体温、顔色、機嫌、せき、鼻水、頭痛、関節痛、体のだるさ、嘔吐(おうと)、便の状態、おしっこの量・色、食欲など全身の状態です。
おしっこの量が少なく、色が濃いときには水分を多めにあげましょう。
こんな症状がみられたらすぐにお医者さんへ
- 痙攣したとき(至急)
- 全身状態が悪くなったとき
- 尿が濃くなったり量が減ったとき(水分を摂取しているにもかかわらず)
- 呼吸が苦しそうなとき
- 熱が続いたり、一度熱が下がったのにまた熱が上がったとき
- 何度も吐き続けるとき
- 眠気が強いとき
- 呼びかけしても反応が弱いなど、異常にぼんやりしているとき
- 首が硬直(こうちょく)して曲がりにくいとき
- 泣き止まないとき
- ふとももを痛がり、歩きづらそうにしているとき
水分補給に気をつけます
熱が高い時は脱水症状にならないよう、まめに水分を与えましょう。
(例)湯ざまし、麦茶、乳幼児用イオン飲料、経口補水液、うすめた果汁、野菜スープなど
熱が高くて食欲がないときは、消化がよく喉ごしのよいやわらかいものにしましょう。お子さんの食べられるものを少しずつ与えます。
(例)おかゆ、うどん、市販の離乳食の利用など
アイスクリーム、プリン、ゼリーなどを与えても大丈夫です。
○おかゆの作り方
5分がゆは米1に対して水5~6の割合
小さな土鍋を使うと簡単
レトルトを使うと簡単)
安静を保ちましょう
なるべく室内で静かに過ごすことが大切ですが、無理に寝かせなくても大丈夫です。
体が楽になるまで抱っこしたり、添い寝をしたりして、お子さんが静かに休めるようにしてあげましょう。
体の抵抗力が下がっていますので、症状があるときは、外で遊ばせることは避けましょう。
部屋の環境に気をつけましょう
室温は暑すぎたり、寒すぎたりしないようにしましょう。室温は秋から冬にかけては20℃前後、夏は26℃~28℃位が適温と言われていますが、基本的には大人が快適と感じる室温でよいのです。
熱があるからと部屋を暖めすぎると室内が乾燥し、余計に辛くなることもあります。ときどき窓をあけ換気したり、ぬれタオルや洗濯物を部屋にかけて湿度を保つなど注意しましょう。加湿器を使う場合は、水をこまめに換えて清潔にしないと雑菌を部屋中にばらまいてしまうことになります。
また、まぶしがるときは部屋を暗くします。
衣類に気をつけましょう
熱が高い時は、布団をかけすぎたり、厚着にしないように気をつけましょう。
背中に手を入れて汗をかいていたら着せすぎです。家の中でも厚着をさせる必要はありません。機嫌がよければ、普段着ている枚数で大丈夫です。
熱が出始めるときは寒気から始まることが多いので、顔色も悪く手足も冷たいときは多めに着せてあげるか、毛布かタオルケットを1枚増やしてあげましょう。
熱が下がってきたら、1枚ずつ少なくしましょう。
清潔にしてあげましょう
熱があり、せき・鼻水等症状がひどい時は、お風呂を控えましょう。お風呂は体力を消耗するため、症状が悪化することもあります。汗をかいたら蒸しタオルで体を拭いたり、こまめに着替えさせたりして気持ちよく寝かせてあげましょう。
熱が下がり、機嫌がもどり、元気が出てくれば、シャワーを利用して体を清潔にしましょう。
目やにがある時は、ガーゼでやさしくとってあげましょう。
電子レンジを使った蒸しタオルのつくり方・・・水で硬く絞ったタオルを耐熱用(たいねつよう)のジッパー付ビニール袋にいれ、1本1~2分加熱するとできあがります。
熱があるときでも無理に冷やすことはありません
熱で、少しつらそうなら、気持ちがよいように冷やしてあげましょう。貼る冷却シートや氷まくらは、熱を下げる効果は期待できません。
お子さんが嫌がらなければ額などに貼り付けて、冷たい感触で気持ちよくしてもかまいません。
保冷剤の小さいものや氷を2、3個ビニール袋に入れてしっかりと口を結び子供の靴下などに入れたもので、首すじや脇の下、足の付け根などにあててあげると熱が下がることもありますし、気持ちがよいです。
外出は十分休養をとってからにしましょう
熱が下がったからといっても、まだ体の抵抗力は弱まっています。体力も消耗(しょうもう)しますので、なるべく室内で静かに過ごすことが大切です。
学校保健安全法及び保育所における感染症対策ガイドラインにより、発症後5日を経過し、かつ熱が下がって2日(幼児は3日)以上経過するまでは出席停止となります。登園・登校時に、治癒証明書等の提出が必要になる場合が多いので、保育園や学校等に確認し、かかりつけ医に相談しましょう。
※日数の数え方は、その現象が見られた日は数えません。その翌日を第1日とします。
予防が大切です
流行中は赤ちゃん連れで人混みにでないようにしましょう。
家族全員が、外から帰ったらうがいや手洗いをしっかりしましょう。
規則正しい生活リズムを守るように心がけましょう。
外来受診時の観察ポイント
以下の点に注意をして、お医者さんに伝えましょう。メモをしていくとよいでしょう。母子健康手帳も忘れずに。
- いつからの発熱か、その後の熱の経過は
- 症状は[機嫌、せき、鼻水、便の状態、嘔吐(おうと)]
- 何か薬を使ったか[いつ、何を]、お薬手帳があれば持参しましょう
- 水分、食事はとれているのか
- おしっこは出ているか
- 家族やお友達など周囲で流行っている病気はないか