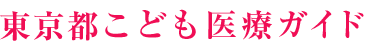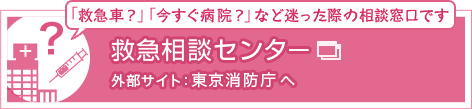子供の薬の一般的注意開く
<子供の薬を理解しましょう>
どうして使うのか、薬の名前、副作用などを理解しておきます。医師、看護師、薬剤師などに確認します。薬局で作ることができる「おくすり手帳」があると、かかりつけ医以外に受診しても、それまでのお薬がわかってとても便利です。また、2つの科にかかったりするとそれぞれに薬が出ることがあるので、同時に使ってよいのかなど相談しやすくなります。何でも気軽に相談できる「かかりつけ薬剤師」をもっているのもよいですね。
<用法、用量を守って使いましょう>
薬の量は子供の体重にあわせて処方されています。大人と同じ薬であっても量が違います。量を間違わないようにしましょう。
<薬を使った前後の観察に努めしょう>
薬の副作用で気分が急に悪くなったり、発疹が出てきたりすることがあります。使った前後の体調の変化に気をつけます。
<自己判断で薬を使わないで相談しましょう>
症状が改善しても使い続ける薬もあります。処方された薬は、指示通りに最後まで飲ませましょう。また症状が同じだからといって勝手に兄弟の使い残しを使うのは厳禁です!薬は一人ひとりに応じて処方されたものです。
<子供の手の届かないところで管理しましょう>
シロップなど甘くしてある薬も多いので、小さな子供が大量に飲んでしまうことにならないようにしてください。
<服用期間が過ぎたら薬を捨てましょう>
常備薬としてとっておく人もいますが、さっさと捨てます。次の病気が同じ状態であるとは限りません。[特にシロップ等はうすめてあるので長く保存できません]
薬の飲ませ方、使い方開く
- 子供の薬にはいろいろ工夫がされています。飲み薬だけではなく、いろいろな経路で吸収されるようにしてあります。
- 小さい子供には、授乳直前や食前に飲ませてあげるとよいでしょう。食後では満腹感で飲まなかったり、吐いてしまったりすることがあります。
- 飲ませる時は体を起こして飲ませます。気管や肺に間違って入らないようにするためです。
- 言葉がわかる子には薬の必要性をきちんと説明します。
<シロップ>
子供が好きな味に甘く調整されています。薬の成分がボトルの底にたまっていることがあるので、均一になるようゆっくり振ってから飲ませてください。
シロップは子供の月齢によって飲ませ方に工夫が必要です。スポイトで与えたり、スプーンを使ったりします。薬に付いている小さなカップが使えればもちろんOKです。後できちんとカップを洗いましょう。
<粉末>
水やぬるま湯に溶けやすく、甘みがついている場合もあります。
粉薬は、口の中全体に広がってむせることもあります。薬を器に入れて水を1~2滴加え、練って飲ませることも工夫の一つです。
<坐薬>
肛門から入れるので水が飲めない状態でも使えます。吸収もすみやかなので効き目がすぐあらわれます。
坐薬は肛門に入れてもすぐに出てきてしまうことがあるので、30秒ほどおさえておきます。
<塗り薬>
湿疹、かぶれ、かゆみ止めなど、皮膚の症状に応じていろいろな種類があります。
2種類以上薬を使う場合、チューブや容器などに、塗る部位と回数などを記入して、間違えないようにします。
薬を塗るときにはまず手を洗い、必要な量の薬を手の甲に乗せます。そして、指を使いうすくのばして使います。
薬の種類ごとによる注意点開く
<解熱剤[解熱鎮痛剤]>
熱が高く、水分や睡眠が十分にとれなかったり、つらそうだったりする時に解熱剤(げねつざい)を使います。解熱剤のなかには子供に使えない薬もあります。必ずお医者さんに処方してもらい、指示に従いましょう。
体温が下がりすぎてしまう[36℃以下が目安]ことがあるので、解熱剤(げねつざい)を使った1時間後くらいにもう一度体温を測っておきましょう。
<抗生物質>
抗生物質は細菌を殺したり、活動を抑える薬です。
決められた日数をきちんと内服することが大事です。具合が良くなって症状が無くなっても、保護者の判断で内服をやめたりせず、お医者さんの指示どおりにきちんと飲みましょう。また、以前と同じ症状だからといって、残っていたものを飲ませることはしないでください。抗生物質がお子さんにとって必要かどうかは、必ず診察を受けてお医者さんに判断してもらってください。
<鎮咳薬[せきどめ]>
せきは喉(のど)や気管にある痰などを外へ出して、体をきれいにします。よって、体にとって必要なものです。
でも、せきがずっと続くようになると呼吸が苦しくてつらくなります。
せきが原因で眠れなかったり食事がとれなかったりするようなときは、かかりつけ医に早めにかかって下さい。
<制吐薬[吐き気どめ]>
主にウイルス性の胃腸炎などによって嘔吐しているときに処方されるお薬です。
内服と坐薬がありますが、嘔吐しているときに飲むのは大変なので、坐薬が使用されることが多いです。吐き気止めは長期にたくさん使用すると、手足が震えたり体がこわばったりする副作用がでることがあるので、処方された量を守って使用してください。