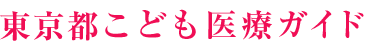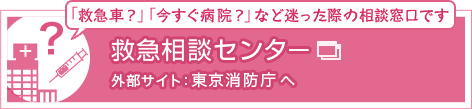基礎情報開く
溶連菌ってなに?
溶連菌の感染により、主に喉に炎症を起こし、高熱や喉の痛みが出現します。全身に発疹が出たり、舌が赤くなったり、中耳炎などを合併することもあります。
正確にはA群β型溶血性連鎖球菌(ようけつせいれんさきゅうきん)、別名では化膿性連鎖球菌(かのうせいれんさきゅうきん)といいます。
緊急度は?
高熱が出たり、喉の痛みが強ければ早めに受診しましょう。
かかりやすい月齢/年齢は?
主に3歳から15歳頃に多いです[ピークは5歳から10歳]。
かかりやすい季節は?
1年中みられますが、冬季と春から初夏にかけて2つのピークがあります。
起こりやすい場所は?
特にありません。
特徴開く
特徴
溶連菌に感染した場合、2~5日の潜伏期の後、主に急性の咽頭炎(いんとうえん)、扁桃炎(へんとうえん)を発症します。高熱と、扁桃(へんとう)の肥大、痛みが特徴です。ひどい場合には食べ物や飲み物を飲み込みにくくなることもあります。
その1~2日後に、全身にかゆみを伴う発疹が出て、舌がイチゴのように真っ赤になり[イチゴ舌]、その数日後の回復期に手や足の指先から皮がめくれてきたりすることもあります[しょう紅熱(こうねつ)]。その他に中耳炎(ちゅうじえん)、副鼻腔炎(ふくびくうえん)、リンパ節炎などを合併することもあります。
また、扁桃(へんとう)の肥大などの症状が治った数週後に、尿が出にくくなって体がむくんだり、血尿や蛋白尿(たんぱくにょう)が出たり[急性腎炎]、いくつかの関節が腫れて痛んだり、心臓の弁膜症(べんまくしょう)を合併したり[リウマチ熱]、さまざまな合併症を引き起こすこともあります。
原因・予防法・治療法開く
原因・予防法・治療法
溶連菌の感染により生じます。
患者のせきやくしゃみ、皮膚への接触により感染します。手洗い、うがい、マスクなどで予防しましょう。
溶連菌に効く抗生剤を使用します。合併症を防ぐため、10日間は抗生剤を続けます。
対処法・家庭でのケア開く
扁桃(へんとう)の肥大、強い喉の痛みなどがあれば早めに受診しましょう。
観察が大切です
<熱を測り、その他の全身の症状を正確に観察しましょう。>
熱があるときは、朝・昼・夕方・夜と1日4回以上測り、熱だけでなく、前回測定した時から、熱の上がり方[急に上がってきた、夕方~夜になると高熱が出る、など]にも注意してみましょう。- 体温の測り方・・・脇の下は汗がたまりやすいのでよく拭き、ななめ前下の方から、脇の下の中央に体温計の先端がくるようにはさみましょう。
- 体調のよい時に熱を測り、お子さんの平熱を知っておきましょう。
- 観察のポイントは、体温、喉の痛み、扁桃(へんとう)の肥大、顔色、機嫌、発疹の状態、頭痛、関節痛、体のだるさ、おしっこの量・色、食欲などの全身の状態です。
- おしっこの量が少なく色が濃いときは、水分を多めにあげましょう。
こんな症状がみられたらすぐにお医者さんへ
- 全身状態が悪くなったとき
- 尿が濃くなったり量が減ったとき(水分を摂取しているにもかかわらず)
- 呼吸が苦しそうなとき
- 呼びかけても反応が弱いなど、異常にぼんやりしている
- 首が硬直(こうちょく)して曲げにくいとき
- 泣き止まないとき
- 耳を痛がるとき
水分補給に気をつけます
熱が高い時は脱水症状にならないよう、まめに水分を与えましょう。
湯ざまし、麦茶、乳幼児用イオン飲料、経口補水液、うすめた果汁、野菜スープなど
食欲がないときは、消化がよく喉ごしのよいやわらかいものにしましょう。お子さんの食べられるものを少しずつ与えます。
(例)おかゆ、うどん、市販の離乳食の利用など
アイスクリーム、プリン、ゼリーなどを与えても大丈夫です。
○おかゆの作り方
5分がゆは米1に対して水5~6の割合
小さな土鍋を使うと簡単
レトルトを使うと簡単
安静を保ちましょう
なるべく室内で静かに過ごすことが大切ですが、無理に寝かせなくても大丈夫です。
体が楽になるまで抱っこしたり、添い寝をしたりして、お子さんが静かに休めるようにしてあげましょう。
体の抵抗力が下がっていますので、症状があるときは、外で遊ばせることは避けましょう。
部屋の環境に気をつけましょう
室温は暑すぎたり、寒すぎたりしないようにしましょう。室温は秋から冬にかけては20℃前後、夏は26℃~28℃位が適温と言われていますが、基本的には大人が快適と感じる室温でよいのです。
熱があるからと部屋を暖めすぎると室内が乾燥し、余計に辛くなることもあります。ときどき窓をあけ換気したり、ぬれタオルや洗濯物を部屋にかけて湿度を保つなど注意しましょう。加湿器を使う場合は、水をこまめに換えて清潔にしないと雑菌を部屋中にばらまいてしまうことになります。
また、まぶしがるときは部屋を暗くします。
衣類に気をつけましょう
熱が高い時は、布団をかけすぎたり、厚着にしないように気をつけましょう。
背中に手を入れて汗をかいていたら着せすぎです。家の中でも厚着をさせる必要はありません。機嫌がよければ、普段着ている枚数で大丈夫です。
熱が出始めるときは寒気から始まることが多いので、顔色も悪く手足も冷たいときは多めに着せてあげるか、毛布かタオルケットを1枚増やしてあげましょう。
熱が下がってきたら、1枚ずつ少なくしましょう。
外来受診時の観察ポイント
以下の点に注意をして、お医者さんに伝えましょう。メモをしていくとよいでしょう。母子健康手帳も忘れずに。
- いつからの発熱か、その後の熱の経過は
- 喉の痛み、腫れの経過は
- 症状は[機嫌、頭痛、関節痛、体のだるさ、発疹]
- 何か薬を使ったか[いつ、何を]、お薬手帳があれば持参しましょう
- 水分、食事はとれているか
- おしっこは出ているか
注意事項開く
注意事項
再発や合併症を防ぐため、途中で勝手に治療を中断せず、かかりつけ医の指示通りに薬を飲みましょう。また、かかりつけ医の許可が出るまで、学校、幼稚園、保育園は休むようにしましょう。
- 基礎情報
- 溶連菌ってなに?
- 緊急度は?
- かかりやすい月齢/年齢は?
- かかりやすい季節は?
- 起こりやすい場所は?
- 特徴
- 特徴
- 原因・予防法・治療法
- 原因・予防法・治療法
- 対処法・家庭でのケア
- 観察が大切です
- 次の場合は、再び直ちに受診します。
- 水分補給に気をつけます
- 安静を保ちましょう
- 部屋の環境に気をつけましょう
- 衣類に気をつけましょう
- 外来受診時の観察ポイント
- 注意事項
- 注意事項