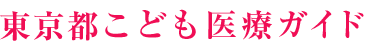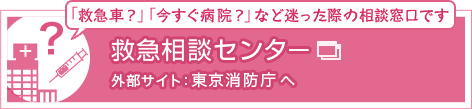基礎情報開く
脳炎・髄膜炎(のうえん・ずいまくえん)ってなに?
脳炎とは、細菌やウイルスが脳に感染して炎症を起こすことです。炎症による脳のむくみのため、圧力が高まってしまって症状が起きます。
髄膜炎(ずいまくえん)とは脳と脊髄(せきずい)[背骨の中を通る神経]を覆っている髄膜(ずいまく)に細菌やウイルスが感染して炎症が起こすことです。髄膜の炎症が脳にも及んだ場合を髄膜脳炎(ずいまくのうえん)といいます。
緊急度は?
緊急でお医者さんを受診します。
かかりやすい月齢/年齢は?
乳幼児にみられることが多いです。
かかりやすい季節は?
ウイルスによる髄膜炎(ずいまくえん)は夏に多くみられるなど、もとになる病気の流行する季節によります。
病気の特徴開く
病気の特徴
発熱とともに、頭が痛くなったり、吐いたりします。意識がぼんやりすることやひきつけを起こすこともあります。赤ちゃんの場合は、頭の骨がまだくっついていないへこみの部分[大泉門(だいせんもん)]が腫れて発見されることがあります。
ウイルス性の場合、症状が軽いことも多いですが、細菌と同じく緊急で受診が必要です。
進行すると意識障害(眠りがちになる、普段どおりの会話や行動ができない)やひきつけを起こすことがあります。
原因・予防法・治療法開く
原因・予防法・治療法
脳炎の原因はほとんどがウイルスです。麻しん、風しん、水痘(すいとう)[水ぼうそう]のときにもみられることがあります。
髄膜炎(ずいまくえん)はほとんどが夏風邪やおたふくなどのウイルスにより体の抵抗力が落ちたときに起こります。麻しんや風しん等の合併症として起こることもあります。
また、細菌によるものもあります。
細菌性髄膜炎(さいきんせいずいまくえん)はまれですが重症の病気なので、緊急で治療が必要です。抗生物質の点滴を行います。ひきつけの薬や脳のむくみを減らす薬を使うこともあります。
ウイルス性の場合は、点滴で水分補給をしたり、痛み止めや吐き気止めを使って症状をやわらげたりします。症状が強い場合は、炎症をおさえる薬を使うこともあります。
単純ヘルペスウイルス感染の場合にはウイルスに効果のある薬をつかいます。
ワクチンで予防
麻しん、風しん、水痘(すいとう)[水ぼうそう]、おたふくかぜはワクチンで予防できます。実際にかかって免疫をつけるよりも、ワクチンを打って免疫をつけるほうが安全です。
細菌性髄膜炎(さいきんせいずいまくえん)は、インフルエンザ菌b型ワクチンと肺炎球菌(はいえんきゅうきん)ワクチンでほとんど予防できます。
対象の月齢になったら、早めにワクチンを受けましょう。
対処法・家庭でのケア開く
発熱に伴って強い頭痛、吐き気、嘔吐(おうと)がある場合には、この病気の可能性があります。進行すると、意識障害(眠りがちになる、普段どおりの会話や行動ができない)やひきつけを起こすことがあります。これらの症状があったら、緊急でお医者さんを受診してください。
生まれてから4~5か月ぐらいまでは症状がわかりにくい
けいれんなど急な症状が起きる前にも、色々な症状がみられることがありますので注意してください。
- おむつ替えで足を持ち上げたり、頭を持ち上げたりするとひどく嫌がる
- 普段より機嫌が悪くて食欲がない
- ちょっとした光や音で泣いたりする
- トロトロ眠りがち(意識障害)になる
- 首の後ろが突っ張る
以上のような症状があるときは、至急お医者さんへ連れて行きます。
入院による治療が基本です
脳炎・髄膜炎(ずいまくえん)の疑いのある時は、入院による治療が基本です。
早期発見・早期治療が大切です
早期発見・早期治療のためには、観察が重要です。しかし、最初のうちは症状がはっきりせず、すぐには診断がつかないこともあります。- 熱の状態、発熱の時期、経過
- 嘔吐(おうと)の状態、経過
- 強い頭痛
- 機嫌、食欲、意識
- 上記に注意して観察し、症状が悪くなる傾向があれば、お医者さんに相談してください。
合併症として併発することがあります
脳炎・髄膜炎(ずいまくえん)は、風邪やおたふくかぜ、麻しん、風しん、水ぼうそうなどの合併症として、ときどきみられることがあります。
これらの病気と診断されたときは、よく観察して、上に書いてあるような症状がみられたら至急受診しましょう。
- 基礎情報
- 脳炎・髄膜炎(のうえん・ずいまくえん)ってなに?
- 緊急度は?
- かかりやすい月齢/年齢は?
- かかりやすい季節は?
- 病気の特徴
- 病気の特徴
- 原因・予防法・治療法
- 原因・予防法・治療法
- ワクチンで予防
- 対処法・家庭でのケア
- 生まれてから4~5か月ぐらいまでは症状がわかりにくい
- 入院による治療が基本です
- 早期発見・早期治療が大切です
- 合併症として併発することがあります