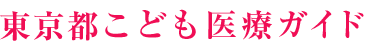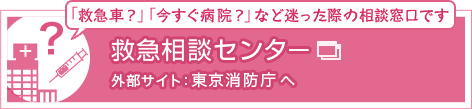基礎情報開く
感染性胃腸炎ってなに?
感染性胃腸炎は、ウイルスや細菌などの病原体が原因で、腹痛、下痢、嘔吐(おうと)、発熱などの症状を起こします。汚染された食品を摂取したり[食中毒]、病原体が人の手などを介して口に入ったときに、感染する可能性があります。病原体の種類により、感染してから発症するまでの時間[潜伏期]が異なります。
治療は、細菌が原因の場合は抗生物質を投与することもありますが、点滴などにより脱水を防ぎ、吐き気などの症状をやわらげる対症療法が中心です。乳幼児の場合、特に脱水を起こしやすいため注意が必要です。
感染性胃腸炎はとにかく予防が大事です。トイレや汚物に触れたあと、子供のおむつ交換のあと、調理や食事の前などにしっかり手洗いをしましょう。また食品は生ものをさけ、中心部まで十分加熱しましょう。
緊急度は?
症状により異なります。水分が十分取れない時は、すみやかにお医者さんを受診しましょう。
かかりやすい月齢/年齢は?
ロタウイルスは5歳以下がほとんどで、特に6か月~2歳ごろに多いです。ノロウイルスは年齢に関係なくみられます。
かかりやすい季節は?
ロタウイルス流行のピークは2~5月にかけてみられ、ノロウイルスは12月~翌年2月に流行します。その他の食中毒は、夏に多い傾向があります。
病気の特徴開く
感染性胃腸炎は、ウイルスや細菌などの病原体が原因で、腹痛、下痢、嘔吐(おうと)、発熱などを引き起こします。
病気の特徴
ロタウイルス
乳幼児のウイルス性胃腸炎の中でも頻度が高いのは、ロタウイルスによるものです。冬から春に流行し、感染すると2-4日の潜伏期間の後、激しい嘔吐(おうと)、発熱で発症し、引き続き米のとぎ汁のような白っぽい下痢になります。 重症化しなければ1週間ほどで治ります。合併症として、けいれん、肝機能異常、急性腎不全、脳症、心筋炎などがあり、意識の低下やけいれんなどがあれば救急受診が必要です。発展途上国ではロタウイルスによる胃腸炎で多くの乳幼児が死亡していますが、わが国でも死亡例が散見され、注意が必要です。2011年頃から乳児に対するワクチン接種が開始されており、効果が期待されます。
ノロウイルス
カキなどの二枚貝を十分に加熱せず食べた場合やウイルス感染した人の便や吐物にさわり、手指を介してウイルスが口に入る場合などに感染を起こします。非常に感染力の強いウイルスで、冬に流行し、感染すると12-48時間の潜伏期間の後、突然の嘔吐(おうと)で発症します。下痢や腹痛、発熱を伴うこともあります。通常は1~2日間で治りますが、その後1週間は便の中にウイルスが出されることがあり、周りの人への感染に注意が必要です。近年、施設・学校・病院などで集団感染が発生しています。
サルモネラ
ニワトリ、ブタ、牛などの家畜からの食肉、卵、牛乳などの食べ物によって食中毒を起こします。
カンピロバクター
家畜に多くいて、特にニワトリの肉からの感染が多いです。犬や猫の便の中にもいて、食べ物や水が汚染されるため、食中毒が発生します。大規模な食中毒の原因になります。
病原性大腸菌
O-157が有名ですが、腸管出血性大腸菌(ちょうかんしゅっけつせいだいちょうきん)の名のごとく、血便が出て激しくお腹が痛みます。夏に多いです。まれに下痢などの症状が出てから4-10日後に、腎臓の状態が急に悪くなり(溶血性尿毒症症候群[ようけつせいにょうどくしょうしょうこうぐん])、重症化し集中治療が必要となることもあります。
原因・予防法・治療法開く
原因・予防法・治療法
主にウイルスや細菌の感染が原因です。
感染性胃腸炎はとにかく予防が大事です。トイレや汚物に触れたあと、子供のおむつ交換のあと、調理や食事の前などにはしっかり手洗いをしましょう。また食品は生肉などの生ものを避け、加熱調理をする場合は中心部まで十分加熱しましょう。
細菌感染が原因の場合は抗生物質を使用することがありますが、点滴などにより脱水を防ぎ、吐き気などの症状をやわらげる対症治療が中心です。無理に下痢を止めると、治るのが遅くなったり重症化したりすることがありますので、下痢止めは使用せず整腸剤を内服する場合が多いです。
乳幼児の場合は特に脱水を起こしやすいため注意が必要です。
わが国でも2011年頃から、乳児を対象としてロタウイルスに対する経口生ワクチンが接種可能になりました。生後2か月から他のワクチンとともに接種を行いますが、初回接種は生後4か月まで(14週6日まで)が推奨されています。
対処法・家庭でのケア開く
何度もくり返し吐く場合、お腹の痛みが強い場合、明らかに脱水が疑われる場合には、すみやかにお医者さんを受診しましょう。
観察が大切
以下の点に注意をして、お医者さんに伝えましょう。メモをしていくとよいでしょう。母子健康手帳も忘れずに。
- 下痢がいつからはじまり、下痢便の状態[回数、量、色]はどうか
- 嘔吐の状態[回数、内容物、血が混じっていないかなど]
- 熱があるときは、朝・昼・夕方と1日3回測り、前回測定したときからの熱の上がり方[急に上がってきた、夕方~夜になると高熱が出る、など]にも注意してみましょう。
- その他観察ポイントは、顔色、機嫌、せき、鼻水、頭痛、関節痛、体のだるさ、おしっこの量・色、回数、食欲など全身の状態です。
- 胃腸炎の原因や、お子さんの状態によって、症状の出かたはさまざまです。
吐いたときは
吐いたときは、吐いたものが気管に入らないように、顔を下か横に向かせて、全部吐かせましょう。吐いたものの臭いでまた吐くこともあるので、汚れ物はすぐに片づけ、口の中をガーゼなどできれいにしましょう。その後は顔を横向きにし、衣類をゆるめて胸やお腹を楽にして休ませましょう。
脱水症状に注意
脱水症状とは・・・- おしっこの量が少ない・おしっこの色が濃い
- くちびるが乾いている
- 手のひらがカサカサしている
- 顔色が悪くぐったりしている
- 皮膚にはりがない
脱水にならないように、水分を根気よく少量ずつ何回も与えましょう。ただし、吐いた後にすぐ水分を与えると、その刺激でまた吐くことがあります。まずは30分~1時間、何も飲ませずに様子をみて、吐かないようなら少しずつ水分を与えましょう。たとえば、湯ざましや麦茶、乳幼児用イオン飲料、経口補水液などを少しだけ与え、しばらく様子をみて、吐かないようなら1回に与える量を増やしていきましょう。ただし、嘔吐(おうと)・下痢がひどい場合には、これらの飲み物だけでは電解質(でんかいしつ)[塩分など]が不足します。かかりつけ医の指示に従いましょう。
おしりを清潔に
市販のおしり拭きなどでこすると、刺激になりただれることもあります。おむつ交換のたびにおしりをシャワーや座浴(ざよく)できれいに洗い流しましょう。おむつをあてる前に、おしりをよく乾燥することも、おむつかぶれを防ぐポイントです。
部屋の環境に気をつけましょう
室温は暑すぎたり、寒すぎたりしないようにしましょう。室温は、秋から冬にかけては20℃前後、夏は26℃~28℃くらいが適温と言われていますが、基本的には大人が快適と感じる室温でよいのです。
衣類に気をつけましょう
熱が高い時は、布団をかけすぎたり、厚着にしないように気をつけましょう。背中に手を入れて汗をかいていたら着せすぎです。機嫌がよければ、普段着ている枚数で大丈夫です。汗をかいたら体を拭いたり、着替えをこまめにし、気持ちよく寝かせてあげましょう。
外出は十分休養をとってからにしましょう
症状がおさまっても、まだ体の抵抗力は弱まっています。体力も消耗しますので、なるべく室内で静かに過ごすことが大切です
ウイルス感染を防ぎましょう
ノロウイルスやロタウイルスは、便や嘔吐(おうと)物にたくさん含まれ、手で触ったりすることで感染がひろがります。便や嘔吐(おうと)物は、マスク、エプロン、ゴムやビニールの手袋をしてきれいに拭き取り、すぐに処分するようにしましょう。できれば、塩素系消毒薬[次亜塩素酸(じあえんそさん)ナトリウム含有]で処理しましょう。その後、手袋をはずし、しっかりと手洗いをしてください。また、タオルは共用しないようにしましょう。ノロウイルスやロタウイルスは、通常のさっと拭くようなアルコール消毒はほとんど効果がありません。
詳しくは、下記のホームページを参考にしてください。
- 感染性胃腸炎(ノロウイルスを中心に) 東京都感染症情報センター
https://idsc.tmiph.metro.tokyo.lg.jp/diseases/gastro/index.html - ロタウイルスに関するQ&A 厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/Rotavirus/index.html - ノロウイルスに関するQ&A 厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_
iryou/shokuhin/syokuchu/kanren/yobou/040204-1.html
注意事項開く
注意事項
ノロウイルスはとても感染力が強く、患者の便・嘔吐物(おうとぶつ)には大量のウイルスが含まれているので、処理をするときは注意しましょう。
- 基礎情報
- 感染性胃腸炎ってなに?
- 緊急度は?
- かかりやすい月齢/年齢は?
- かかりやすい季節は?
- 病気の特徴
- 病気の特徴
- 原因・予防法・治療法
- 原因・予防法・治療法
- 対処法・家庭でのケア
- 観察が大切
- 吐いたときは
- 脱水症状に注意
- おしりを清潔に
- 部屋の環境に気をつけましょう
- 衣類に気をつけましょう
- 外出は十分休養をとってからにしましょう
- ウイルス感染を防ぎましょう
- 注意事項
- 注意事項