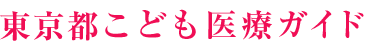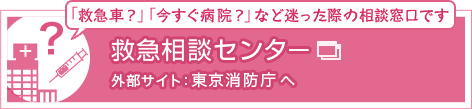肺炎ってなに?
肺に細菌やウイルスが感染することで、せき、熱、呼吸困難といった症状を起こす病気です。
呼吸が速くなったり、乳児だと不機嫌になったりおっぱいを飲む元気がなくなったりします。
緊急度は?
呼吸がつらそうなとき、顔色が悪いとき、ぐったりしているときは救急の受診が必要です。
かかりやすい月齢/年齢は?
どの年齢でもかかりますが、原因となる微生物の種類によりかかりやすい年齢は異なります。RSウイルスは3歳くらいまで、マイコプラズマは5歳以上に多いです。
かかりやすい季節は?
冬が多いです。
病気の特徴
熱、せき、苦しそうな呼吸、呼吸が速いといった症状を起こします。
症状だけでは風邪や気管支炎と見分けがつかないことが多いです。
診断には胸のレントゲンの検査、状態によっては胸部CTスキャンが必要になることもあります。
原因
インフルエンザウイルスやRSウイルスなどの風邪のウイルスが原因となることが多いです。肺炎球菌といった細菌やマイコプラズマによるものもみられます。
予防法
ウイルスがつかないように日頃から手洗いをよくしておきましょう。家族にせきをしている人がいるときはマスクをしたり、違う部屋で過ごすように心がけてください。
予防接種で防ぐことも可能な病気もあります
麻しんや水痘〔みずぼうそう〕の合併症としての肺炎もあります。
百日せきも三種混合や四種混合ワクチンを接種していない乳児は肺炎を起こします。インフルエンザやインフルエンザ桿菌・肺炎球菌もワクチンがあります。積極的にワクチンを接種して、子供と周囲の人を感染から守りましょう。
治療法
細菌による肺炎は抗生物質が必要です。比較的元気で呼吸困難が強くない場合には飲み薬で治療できることもありますが、入院して点滴で治療しなければならないことが多いです。
ウイルスによる肺炎は抗生物質が効きませんが、細菌とウイルスの両方が感染していることもあるため、抗生物質を使うこともあります。
こんな症状が見られたらすぐにお医者さんへ
- 呼吸が小刻みで速い(ハーハーと浅い息をする)
- 呼吸が苦しそう
- 鼻がふくれたり縮んだり(小鼻をピクピク)、あえぐような呼吸をする
- 息を吸うときに首の正面やあばら骨の間がへこむ
- 肩で息をする
- うめくような呼吸
- 激しくせきこむ
- 水分がとれない
- 顔色が悪い、ぐったりしている
風邪の症状が長引くときは肺炎になっている可能性があるため、日中の診療時間内に小児科を受診しましょう。ただし、呼吸がとても苦しそうならば、時間帯にかかわらず速やかに受診しましょう。
観察が大切です
風邪との区別が難しいことが多いです。
熱を測り、その他の全身の症状を正確に観察しましょう。
熱があるときは、朝・昼・夕方・深夜と1日4回測り、熱だけでなく、前回測定したときからの熱の上がり方[急に上がってきた、夕方~夜になると高熱が出る、など]に注意してみましょう。
観察ポイントは、体温、せき、呼吸、顔色、機嫌、鼻水、頭痛、体のだるさ、嘔吐(おうと)、便の状態、おしっこの量・色、食欲など全身の状態です。
せきが出るときの対応
- 痰が切れやすくするための工夫をとりましょう
- 背中や胸を軽くとんとんたたく
- 十分に水分を補給する
- 保温と湿度に注意をはらう
- 衣類をゆるめ、上体を起こし加減にする
水分補給に気をつけます
熱とせきにより脱水状態になることがあるので、十分な水分を与えましょう。一度に飲ませると、せき込んだときに吐いてしまうことがあるので、少しずつこまめに水分を与えましょう。湯ざまし、麦茶、幼児用イオン飲料などがよいでしょう。水分補給は、気道にうるおいを与え、痰がきれやすくなるという需要な効果があります。
部屋の環境に気をつけましょう
室温は暑すぎたり、寒すぎたりしないようにしましょう。室温は秋から冬にかけては20℃前後、夏は26℃~28℃位が適温と言われていますが、基本的には大人が快適と感じる室温でよいのです。
熱があるからと部屋を暖めすぎると室内が乾燥し、余計に辛くなることもあります。ときどき窓をあけ換気したり、ぬれタオルや洗濯物を部屋にかけて湿度を保つなど注意しましょう。加湿器を使う場合は、水をこまめに換えて清潔にしないと、雑菌を部屋中にばらまいてしまうことになります。
また、まぶしがるときは部屋を暗くします。
衣類について気をつけましょう
熱が出始めるときは寒気がきてふるえること(悪寒戦慄)から始まることが多いので、顔色も悪く手足も冷たいときは多めに着せてあげるか、毛布かタオルケットを1枚増やしてあげましょう。
熱が下がってきたら、1枚ずつ少なくしましょう。
汗をかいたら体を拭いたり、こまめに着替えをしましょう。
外出についてはかかりつけ医とよく相談して決めましょう
体力の消耗をしていますので、なるべく室内で静かに過ごすことが大切です。
かかりつけ医と相談しましょう
外来受診時の観察ポイント
以下の点に注意をして、お医者さんに伝えましょう。メモをしていくとよいでしょう。
母子健康手帳も忘れずに。
- いつからの発熱か、その後の熱の経過は
- 呼吸やせき、痰の状態
- 他の症状は[機嫌、鼻水、便の状態、嘔吐(おうと)]
- 何か薬を使ったか[いつ、何を]、お薬手帳があれば持参しましょう
- 水分、食事はとれているか
- おしっこは出ているか
注意事項
- 持病のある人は重症化しやすいので、特に注意しましょう。
- ちゃんと治さないとぶり返すこともあります。特に抗生物質に関しては、親の判断で中止せず、かかりつけ医と相談してから中止しましょう。