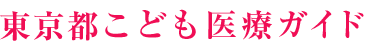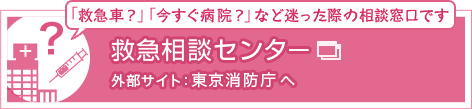概要開く
母乳・ミルクの与え方や離乳食のすすめ方には、一応の目安はありますが、子供の健康状態や家庭の事情など、個々の状況に合わせて工夫することが必要です。
母乳・ミルクの飲ませ方開く
できるだけ母乳で育てましょう
母乳には赤ちゃんとお母さんの双方に次のようなメリットがありますので、できるだけ母乳を飲ませるようにしましよう。
- 母乳は最適な栄養源
- 免疫物質が含まれる
- アレルギーを起こしにくい
- 産後のお母さんの体の回復を早める
ただし、母乳だけでは足りなかったり、赤ちゃんやお母さんの事情で母乳を飲ませてあげられないときは、市販されている育児用ミルクを使用します。市販されているミルクは母乳の成分に近いものになるよう調整されていますので、市販のミルクでも調乳法を守れば、母乳と同じように発育します。あまり母乳にこだわらず、安心して飲ませてあげてください。
お母さんの心が落ち着き、スキンシップを図ることが大切です。授乳の時間は、できるだけ抱っこして優しく声をかけ、スキンシップをとるようにしましょう。
授乳のタイミングと量
通常は、お産をした医療機関で、医師や助産師から授乳の指導を受けて飲ませます。
生まれたての赤ちゃんは無意識、無自覚に泣いたり、しかめ面をして「おっぱいが欲しい」というサインをお母さんに送ります。お母さんがこのサインをキャッチし授乳を行うことで、赤ちゃんは自分の出したサインの意味を学習すると考えられています。そして、お母さんの体は赤ちゃんのサインに反応して、授乳をくり返し、生後6~8週間で赤ちゃんの必要な時に必要な母乳量を作りだせるようになります。この自然な授乳や哺乳(ほにゅう)のリズムの確立が大切です。
ですから、原則的には赤ちゃんが欲しがったら飲ませましょう。出生後から生後2、3か月頃は、欲しがる時、1日7、8回以上が目安です。生後3~5か月頃では、眠る時間が長くなり授乳回数も1日6、7回くらいに減ります。
飲む量が少ないと心配になりますが、お母さんの母乳分泌のリズムや赤ちゃんの哺乳(ほにゅう)量には個人差があります。赤ちゃんが元気で体重が増加しているのであれば心配いりません。
また、母乳を十分に分泌させるためには、お母さんがバランスのよい食事をとることも大切です。
薬の影響
お母さんが飲んだ薬は母乳にも分泌されます。お母さんが薬を服用する場合は、必ず医師や薬剤師に授乳中であることを相談して、処方してもらいましょう。薬の種類や量によっては影響があまりない場合もあります。
アルコール・たばこの影響
お母さんが飲んだアルコールやたばこは母乳にも分泌されます。授乳している期間はお酒はやめましょう。たばこも、母乳を介してニコチンなどの有害な化学物質が赤ちゃんに吸収され、成長や発達に影響を与えると言われています。さらに、家族などに喫煙者がいる場合では、そのたばこの煙が赤ちゃんの健康に影響を及ぼします。
また、両親が喫煙する場合に、乳幼児の死亡のひとつである「乳幼児突然死症候群[SIDS]」の発症率が高くなるというデータがあります。赤ちゃんのそばでは絶対禁煙です。お母さん自身の禁煙はもちろん、身近な人の理解を得ることも重要です。
乳幼児突然死症候群[SIDS]とは
元気ですくすく育っていた赤ちゃんが、眠っている間に突然亡くなる病気です。原因はわかっていません。日本ではおよそ出生6,000~7,000人に1人と推定されていて生後2か月から6か月に多く、まれに1歳以上でも発症することがあります。
育児用ミルクの調乳
お母さん自身の病気や飲んでいる薬の影響で母乳を与えられないときなど、市販のミルクを足したり、市販のミルクだけ与えることになります。ミルクのつくり方は、製品によって決められた通りの濃さに溶かすことが大切です。
ミルクの調乳の前には必ず手を洗い、やけどに注意をしながら一度沸騰(ふっとう)させた70℃以上のお湯でミルクを溶かし、体温くらいまで冷ましてから飲ませるようにしましょう。表面が冷めていても中心部は熱いことがあるため、何度か振って確認してください。飲み残しや調乳後2時間以上たったミルクは必ず捨ててください。
また、赤ちゃんのミルクや水分補給には、水道水、水質基準に合格した井戸水や、ミルク調乳用の密封容器に入った水などを念のため一度沸騰(ふっとう)させてから使いましょう。
ほ乳瓶の消毒
消毒の方法は、蒸したり煮沸(しゃふつ)する方法や薬液につける方法、専用容器に入れて電子レンジを利用する方法などがありますが、使いやすいものを選んで行ってください。
いずれの方法でも大切なことは、哺乳瓶(ほにゅうびん)を使った後によく洗うことです。特に、乳首の中やびんの底など、ミルクかすがつきやすい場所は清潔な専用のブラシでよくこすって汚れを落します。できれば使うたびに洗うのが理想的です。まとめて洗う場合も、使用直後にミルクの残りを捨てて、さっと流しておきましょう。
搾乳(さくにゅう)・冷凍母乳
何らかの理由で直接授乳が行えない場合、お母さんが仕事をしている場合などは、搾乳(さくにゅう)[母乳を手で搾(しぼ)ること]が必要です。
搾乳(さくにゅう)するときには手を石けんと流水で綺麗に洗い、乳首と乳房をお湯で絞(しぼ)ったタオルで拭いてから、乳輪部を押すようにして搾(しぼ)ります。直接ほ乳瓶に搾(しぼ)るか、口の広い容器に搾(しぼ)ったものをほ乳瓶に移してもかまいません。専用の搾乳(さくにゅう)機を使ってもよいでしょう。
仕事の都合で保育者に母乳を飲ませてもらう場合などは、専用のパックに母乳を移し、すぐに冷凍します。飲ませる時には流水で解凍し(水は2~3回かえる)、ほ乳瓶に移してから40℃前後のお湯を用意して湯煎(ゆせん)にかけ、人肌程度に温めます。
牛乳・フォローアップミルク
赤ちゃんのさまざまな機能が未熟なうちに牛乳を与えると、鉄欠乏症(てつけつぼうしょう)になることがあります。牛乳を飲ませるのは、1歳を過ぎてからにしましょう。しかし、プレーンヨーグルトと同様に生後7~8か月頃から離乳食の材料として牛乳を利用することは差し支えありません。
フォローアップミルクは母乳やミルクの代替品ではなく、牛乳の代用品として開発されたもので、牛乳に不足している鉄とビタミンを多く含んでいます。離乳食が順調に進まず、鉄不足のリスクが高い場合などに使用するのであれば、生後9か月以降にとり入れます。母乳やミルクをやめてフォローアップミルクに切り替える必要はありません。
離乳食の進め方開く
離乳食の進め方[概要]
母乳やミルクだけに頼っていた赤ちゃんに、なめらかにすりつぶした状態の食べ物を与えはじめ、しだいに食べ物の固さと量、種類を増やして幼児食に近づけていくことを離乳といいます。
食べものを噛みつぶしたり飲み込んだりできるようになり、食べられる食品も増え、やがて自分で食べられるようになります。赤ちゃんにとって「離乳」は、自立への一歩といえます。
離乳食をどんどん食べる子や食の細い子、また、好き嫌いがある子など一人一人の個性も出てきます。離乳は、赤ちゃんの成長、発達の様子をよく見て、その子に合わせて進めていきましょう。また、生活リズムを身につけ楽しい雰囲気で食べる楽しさを体験していくことは、子供の「食べる力」を育むことにつながります。
離乳食の開始
離乳はいつから始めればいいのでしょうか。
赤ちゃんの発達には個人差がありますから、赤ちゃんの様子をよく観察しましょう。生後5、6か月頃になり、
- 首すわりがしっかりしている
- 支えてあげると座れる
- 食べものに興味を示す
- スプーンなどを口に入れても舌で押し出すことが少なくなる
などの様子がみられたら、離乳を開始しましょう。初めはうまくいかなくても、だんだん上手に食べられるようになりますから、あせらず、楽しい雰囲気で少しずつ進めていきましょう。
離乳食の進め方
[生後5、6か月頃]
離乳食は1日1回から始めます。離乳開始から1か月間くらいは、離乳食の舌ざわりや食感に慣れ、上手に飲み込めるようになることが目的です。赤ちゃんの様子を見ながら1さじずつ与えましょう。母乳やミルクは飲みたいだけ飲ませます。
[生後7、8か月頃]
離乳開始後、1か月を過ぎた頃から、舌でつぶせる固さのものを1日2回の食事のリズムをつけて与えます。また、いろいろな味や舌ざわりを楽しめるように、食品の種類を徐々に増やしていきましょう。
[生後9~11か月頃]
1日3回の食事のリズムを大切に、家族一緒に楽しい食事ができるようにしましょう。9か月以降は、鉄分が不足しやすいので、赤身の魚や肉、レバーを取り入れ、調理に使用する牛乳・乳製品の代わりにミルクを使用するなど工夫しましょう。固さは歯ぐきでつぶせるものを与えます。
[生後12~18か月頃]
1日3回の食事のリズムを大切に、足りないようであれば、おやつを1~2回時間を決めて与えます。また、手づかみ食べなどで、自分で食べる楽しさを体験させてあげましょう。形のある食べものを噛みつぶして食べられるようになり、エネルギーや栄養素の大部分を母乳やミルク以外の食べものから摂れるようになれば、離乳は完了です。
※注意しましょう!
はちみつにはボツリヌス菌が入っていることがあり、乳児期に感染すると「乳児ボツリヌス症」を起こす恐れがあるので、1歳になるまでは使わないでください。
離乳の開始前に果汁は必要なの?
離乳前の赤ちゃんにとって最適な栄養源は母乳やミルクです。離乳の開始前に果汁を与えることについて栄養学的な意義は認められていません。果汁などの乳汁以外の味やスプーンに慣れるというのも、離乳が開始してからで十分です。むしろ、赤ちゃんの発達からみるとそのほうが受け入れやすいといえます。
離乳食の進め方の目安
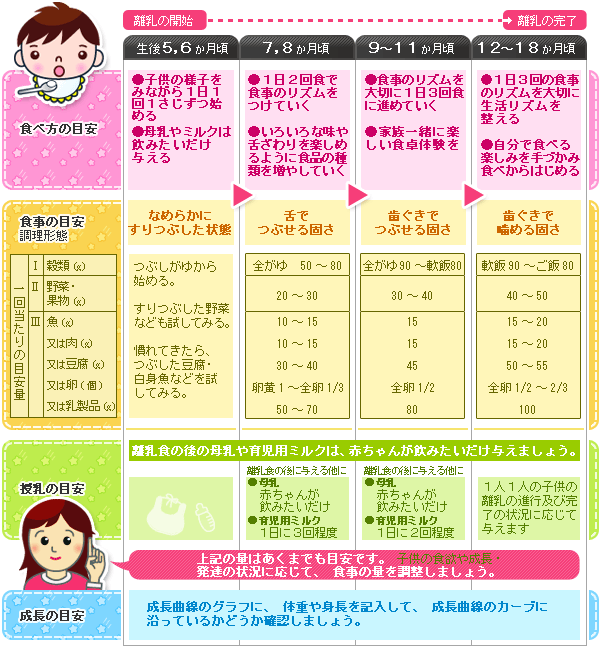
厚生労働省「授乳・離乳の支援ガイド」[平成19年3月]から一部改変して抜粋
ベビーフードの使い方
全ての食事を手作りできれば理想的ですが、市販のベビーフードを利用してもかまいません。離乳食の固さや舌ざわりを試したり、料理の素材として利用することもできます。また、旅行の時や他人に預ける時など、調理がしづらい時に利用する方も多いようです。
ベビーフードには、水や湯を加えてもとの形状にして食べるドライタイプのものや、瓶詰・レトルト食品などのウエットタイプの2種類に大別され、いろいろな製品があります。また、「りんごの裏ごし」などの単独の素材のものから、「クリームシチュー」などの調理済みのものまで、調理の種類もさまざまです。製品の表示をよく確認して、赤ちゃんの月齢や離乳の進み具合にあったものを選んで、上手に利用するようにしましょう。
離乳の完了
形のある食べものが食べられ、栄養の大部分が母乳やミルク以外の食事からとれるようになった状態を「離乳の完了」といいます。その時期は生後12か月~18か月頃です。
この頃には食事は1日3回となり、その他に1日1~2回の間食[おやつ]を目安とします。咀(そ)しゃくの機能は、奥歯が生えるにともない乳歯の生え揃(そろ)う3歳頃までに獲得されます。
引用・参考文献:授乳・離乳の支援ガイド[平成19年3月]厚生労働省
授乳・離乳の支援ガイド 実践の手引き[公益財団法人 母子衛生研究会]